眼差しで勝負・・・石井裕也監督の映画観

「例えばチャップリンの作品のように・・・」(石井裕也監督)
──主演の松田龍平さんはいかがでした?
そうですね、存在感とかもちろん素晴らしいですけど、今回は少し特殊な存在でした。
──というと?
初めに言ったように、まずプロデューサーからお話をもらったときに、「監督はお前、主演は松田龍平」と言われていたので、なんだか最初から2人セットで決まっていたような気がして、監督と主演俳優というよりも、一緒にこの作品を創りあげる共闘する仲間のような意識がずっとありました。実は年齢も同じなので特にそういった感じが強かったのかもしれませんが。
──監督と主演が同い年というのはけっこう珍しいかも。同い年ということにどんな意味があったと思われますか?
そうですね、育った場所も環境も全然違うのですが、どこか感覚的に共通する部分はあったように思います。2人とも今年30歳で、主人公の馬締は映画のなかで27歳から42歳になるわけですが、27歳の馬締については自分も松田さんもよくわかるんです。自分たちが数年前に見ていたものを彼にも見せればいいわけですから。でも、42歳はわからない。どんな風景をどんな感性で見ているのか想像するしかないわけです。そんなとき2人で言っていたのは、馬締ってかっこいいよなっていうことでした。ひとつのことをやり続けているってかっこいいじゃないですか。
──たしかに。
そういう人への羨望とか、憧れはあるので、自分たちの理想を42歳の馬締に投影した部分はあります。でも、一方で、今の自分たちの感性も大事にしたいというか、いくつになっても変わりたくないという気持ちも同時に入っています。そのアプローチの仕方は二人とも一致していたように思います。でも、同い年の男同士って、意見がぶつかったときにはお互いに引き方がわからないところがあって、そこはちょっと困ったかな(笑)。
──42歳の馬締はかっこいいけど、すべてが理想的というわけではないということですね。
そうです。理想の一部は入っているといった感じですね。

──なるほど。宮﨑あおいさんはどうでした?
ひとことで言えば、すごい女優さんですよね。技巧派と感覚派という分け方があるとすれば、宮﨑さんはその両方を兼ね備えているんです。すごい技術を持っているけれどもそれは深い感覚に裏打ちされているといった感じ。それに反射神経がいいというか頭の回転が速い。なんでもできるし、しかも柔軟性がある。やっぱりすごい女優さんです。
──今回、松田龍平、宮﨑あおいという実力派俳優を迎え、公開劇場もメジャー系列で製作費も宣伝費も大きい。石井監督としては「よしっ、やってやるぞ!」っていう気負いのようなものはあったのですか?
ウーン、あったと思うんですけど。なんていうのかな、そういうところも馬締のキャラクターに引っ張られてしまったというか、「よっしゃー!」って声高に言うのではなくて、「うん、やれることをちゃんとやろう」と小声で決意するみたいな(笑)。そんな気持ちで、松田さんと現場にいたような気がします。
──脇を固めるのはオダギリジョー、小林薫、加藤剛。豪華だけど渋い感じもする素敵な布陣です。
オダギリさん演じる西岡という役は、馬締を相手にチャラいというか、お調子者的なことを言う役なのですが、馬締のリアクションは基本的に変わらないわけなんです。そういう能力のない人物ですから。だから、西岡の役はすごく難しいんです。芝居が過剰になってしまう危険性があるから。やり過ぎてしまう可能性がある。でも、自然に見えるのはオダギリさんの力量ですよね。小林さんは現場で“このセリフはこう変えたほうがいいんじゃないか”とよく言ってくださって、それが“確かに”と言えるものが多かったです。脚本をよく読み込んできてくださってるな、と思いました。加藤さんは、語弊を恐れずに言えば、とても良い老い方をしてらっしゃる感じがしました。あの世代で肉食的な感じのする俳優さんは多いのですが、加藤さんはそうじゃなくて、文学の香りがする、良い年齢の刻み方をしておられる。辞書作りの要となる国文学者にぴったりでした。
──あともう一人。個人的にぜひお訊きしたかったのが、辞書編集部のベテラン・パート部員を演じられた伊佐山ひろ子さんのことなんです。
そこが気になっている方、多いみたいですね(笑)。

──ぼくらのような、1970年代の日活ロマンポルノ世代には、時代のアイコンでもあった女優さんですから。伊佐山さんの起用は監督の提案ですか?
いえ、違います。ぼくは伊佐山さんのことはよく存じ上げなかったんです。あの役の候補者を考えているときに、誰かが伊佐山さんの名前を出してくれて。資料を見せてもらっていいなと思ったんです。
──50代以上の日本映画ファンにとっては、いい意味で作品のちょっとしたアクセントになってます。監督はさきほど、ご自分の領域をこの作品で広げていきたいとおっしゃてましたが、この作品でキャリアが少し変わっていきそうな予感のようなものはありますか?
小林さんや加藤さん、それに伊佐山さんのようなベテランの俳優さんたちやスタッフさんたちと一緒に仕事をさせてもらって、とてもいい経験にはなりましたが、この作品で監督としての自分がなにか変わる予感というと、正直言って特にはないですね。自分のところにきた仕事を、これからもきちんとやっていくだけです。
──初めての原作ものでしたが、やってみて、やはり自分で脚本からやったほうがいいなと改めて思ったりはしませんでしたか?
それはまったくないです。仕事に応じて一番適したやり方でやればいいと思います。自分で脚本から書く場合もあるでしょうし、原作モノもあるでしょうし。どちらかに特化してしまうのは領域を狭める気がします。
──最後に少し難しい質問をさせてください。石井監督は、ご自身をどのような監督だと思っていますか?
そうですね。テクニックで勝負はしてないと思います。では、なにで勝負しているかと言うと、人や出来事をどのように見つめているか、その視座というか眼差しというか、そういったところだと思っています。それは、ぼく自身がこれまで、過去の多くの映画で感動してきたところなんです。派手なアクションとかかっこいいカメラワークとかカット割りとかではなくて、例えばチャップリンの作品のように、人をどのように見つめているか、それが伝わってくるチャップリンの眼差しに感動してきたんです。だから、ぼく自身もそこで勝負する監督としてやってきたつもりだし、ずっとそうありたいと思っています。
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
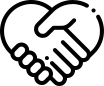 コラボPR
コラボPR
-

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版
NEW 2025.3.31 16:45 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
NEW 2025.3.31 13:00 -
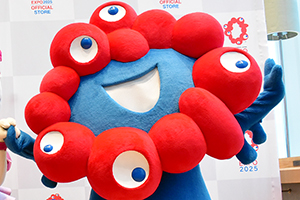
大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】
NEW 2025.3.31 06:00 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]
NEW 2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]
2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]
2025.3.29 07:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.28 16:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
2025.3.28 14:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]
2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ
2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]
2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.24 10:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.3.19 10:30 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]
2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]
2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]
2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.7 14:00 -

今が旬!大阪難波であまおう苺のアフタヌーンティー[PR]
2025.3.6 17:00 -

万博まで待てない!神戸でサウジアラビアパビリオンを体験[PR]
2025.3.6 12:00 -

万博内2番目に大きなパビリオン!サウジが難波に[PR]
2025.3.5 17:00 -

高速料金が乗り放題でお得!ぐるっとドライブパス[PR]
2025.3.1 10:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア













 ピックアップ
ピックアップ







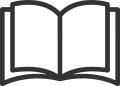 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

