大森監督・井浦新・瑛太が語る「表現」

過去の忌まわしい記憶に翻弄される離島出身の3人を通して、人間の心の底にある闇を描いていた、三浦しをんの小説『光』が映画化。メガホンをとったのは、三浦作品『まほろ駅前多田便利軒』でもタッグを組んだ大森立嗣監督。主人公とその幼なじみを演じたのは、井浦新と瑛太という実力派コンビ。圧倒的な暴力を描いた本作について、また、近年の映画作りについて3人に話を訊いた。
取材・文/田辺ユウキ 写真/木村正史
「映画の作り方をぶっ壊した」(大森立嗣監督)
──この映画でまず重要なのは、主人公である信之、輔の出生地の島の存在。閉塞感があり、ジメッとしていて。そこで起きた出来事から逃れられなくて、そのトラウマが地続きになっている。何か、ずっと息苦しいですよね。そういった物語と、今の現実社会の行き詰まった雰囲気がリンクして見えました。
大森「現在って何事にも理性的になりすぎているんじゃないか、とずっと感じていたんです。やたらとコンプライアンスという言葉をうるさく言われるし、やってはいけないことが多い。もしくは、過剰に自己規制を敷いたりしますよね。そういうなかでこの映画は、理性ではなくもっと本能的な部分に光を当てたかったんです。そうすればもう少しは生きやすくなったり、幸せになったりできるんじゃないかなって」

──それって、今の映画作りの状況の話にも繋がってきますね。
大森「僕自身、映画作りで『これはやっちゃいけない』と考えたりはしません。でも挑戦的なことをやろうとすると、現実問題として制作費が集まりにいくい状況はあります。僕はそれをどうにかしてうまく改革したいんです。作り方を含めて考えていかなきゃいけない。そのなかの1本として、『光』はあります。これは自分自身の映画の作り方をぶっ壊したので」
井浦「確かに、仕事や表現の場でもそういった息苦しさや不条理さを感じることはあります。押さえつけられることもあるし、それをかい潜ってうまくやれたりもするけど、でもそうすると心に傷として残るんです。それで最悪なのは、後悔になること。純粋じゃなくなり、自分が汚れていってしまう気になるんです。役者としては、表現者として必要なことは何だってやりたいですけど、表現は純粋なものではなくてはやはりいけないと思います」
瑛太「自分で責任がとれるかどうかですよね。それでキャリアが終わるなら、それが才能の限界、終着点なんだと思います。今と昔では当然、社会のシステムが違う。ちょっとしたことでもスマホで撮られて、拡散されて。もう、気にしていると生きていけないですよね。僕は、そういった現在の状況から解放されたい瞬間があります。趣味などで、うまく気持ちを逃がしていますが。それでもやっぱりどこかで、(そういう社会に)憤りはありますけど」
──おふたりが演じた信之、輔というのは、まさにそういう人物像ですよね。苦しいけど、なんとか生き続けなきゃいけない。すごく本能的なキャラクターだと思ったんですが、演じる上ではこんなに難解なことはないと思います。
井浦「監督がおっしゃったように、僕自身も理性的なものに対して何かを突きつける映画にしたいと考えていました。でも口裏を合わせたりすることはなく、本当に本能的な動きになっていましたね。むしろ理性的な芝居はなかった。そこさえも考えていなくて、心のままにやっていました。だから先ほど、自分自身の考え方について答えましたが、『もしかすると、(自分の考え方が)役にも出ていたかもしれない』と気付きました」
瑛太「(輔に関しては)自分の考え方が反映されていたかどうかは分かりませんが、それでもチャレンジしたい気持ちがありました。次のステージにいくために、自分の芝居の癖や概念を超えていきたかった。タツさん(大森監督)とは、以前ご一緒した『まほろ駅前』シリーズを超えるような作品にしたかったし。新さんとは初共演なので、どうすれば新さんの刺激物になれるかずっと考えていた。そういったことを踏まえた上で、今回の役は日々の生活の延長線上にあったので、憤り、息苦しさを芝居で出したかった」
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
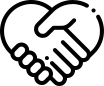 コラボPR
コラボPR
-

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
NEW 2025.4.10 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
NEW 2025.4.10 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
NEW 2025.4.10 11:00 -

大阪土産に悩んだら…これだ!駅近で買える人気5選[PR]
NEW 2025.4.9 07:00 -
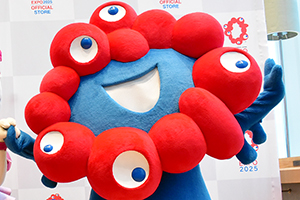
大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】
2025.4.7 06:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.4.2 19:30 -

春は桜も!ガイドブックにもない、淡路島秘境ツアー[PR]
2025.4.2 07:00 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】
2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版
2025.3.31 16:45 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]
2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]
2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]
2025.3.29 07:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]
2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ
2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]
2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.24 10:00 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]
2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]
2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]
2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.7 14:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年上半期の運勢は?
2024.12.29 20:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア














 ピックアップ
ピックアップ







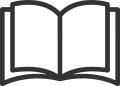 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

