10年ぶりの長編、照屋年之監督「やっとチャンスをいただいた」

お笑い芸人・ガレッジセールのゴリが、本名の照屋年之(てるや・としゆき)名義で監督・脚本を手がけた映画『洗骨』。実は10年前にも長編映画『南の島のフリムン』を撮っているが、(一部評論家から絶賛されたものの)興行的に振るわず、なかなか次の作品を手掛けることができなかった。それでも諦めることなく、自らも出資して自主映画を撮り続けてきた。あれから10年。映画監督・照屋年之の才能を、いよいよ日本中に知らしめるときがきた。
取材/ミルクマン斉藤
「絶対、これを映画にすべきですと」(照屋監督)
──実は僕、監督が撮った『南の島のフリムン』(2009年)が大好きなんです。その年のベスト10にも入れたと思うんですけど、あれがなぜ過小評価されているのかと(笑)。
ええ!? めっちゃうれしいっす! 初めてかもしれない、そんなこと言ってくれる人。知り合いに、「東京の劇場に観に行ったら、お客さん2人だった」と言われたときは泣きそうになったんですよ。せっかく一生懸命作ったのに、誰にも注目してもらえないんだって。いやぁ、報われた・・・この10年が報われました!

──先日、改めて観たんですが、やっぱりすごく面白いです。コメディとしてはもちろん、いろんな意味でも。だからテレビで芸人のゴリさんを見るたびに、なぜ次作を撮らないのかなと心待ちにしてたんですよ。
はぁ~、めっちゃうれしい。これまで撮れなかったのは、あれがコケたからです(苦笑)。ヒットしないと次が来ないシビアな世界じゃないですか。それでも撮りたいから、自分自身もお金出してずっと自主映画を撮ってたんですよ。そしたら、『沖縄国際映画祭』で『born、bone、墓音。』という短編映画で賞をいただいて。それでやっと、長編映画のチャンスをいただいたという。
──沖縄映画って、一時期ブームみたいになりましたよね。でも、リゾート映画になったり、あるいは基地問題とかのヘヴィな話になったり、どうしても本土の人間が撮るとそうなりがちで。また、沖縄の作家が撮っても、民俗的・伝承的なユニークさに傾く映画になる。でも、『南の島のフリムン』は違ったんです。例えば、豚の下ネタにしても、米軍基地や米国兵との関係にしても、沖縄県民以外にはなかなか撮りにくいようなあっけらかんさがありますよね。
いや~、ちょっと飲みに行きますか、取材止めて(笑)。
──そうしたいところですが(笑)。で、今回も「洗骨」という極めて特殊な習俗を扱ってられますよね。僕は1960年代に芸術家・岡本太郎さんが沖縄に行って、それを写真に撮られたことで勃発した「週刊朝日事件」くらいでしか知らなかったんですけど。しかし監督も、この長編の原型となった『born、bone、墓音。』の舞台が沖縄・粟国島に決まるまで、ご存じなかったらしいですね。
うちのかぁちゃんが亡くなったときも火葬ですし、沖縄もそれが当たり前で。それを教えてくれたプロデューサーに何回も訊きましたもん。「洗骨? へ? 燃やさない? このご時世ですよ? 平成ですよ? 法律に引っかからないんですか? 闇でやってる火葬方法ですか?」って。それで、「洗骨」を経験した島のおじぃおばぁに何人もインタビューして。
──実際にリサーチされたんですね、監督自身で。
いやぁ、こんなすごい風習が残ってるんだってびっくりして。昔は沖縄全部でやってたというんです。てことは、僕の祖先を辿れば、みんな「洗骨」を経験してるわけじゃないですか。実はすでに、粟国島で撮るドタバタコメディの脚本ができてたんです。でも「絶対、これを映画にすべきです。この脚本は捨てましょう!」ってイチから作り直して。最初は怖かったんですよ、ミイラにして骨を洗うなんて。でも、おじぃおばぁに話を聞くと、全然怖くなくて、亡くなった人への愛しかないんです。その愛の根底を前半で描ければ、「洗骨」シーンになったとき、骸骨さえも愛おしく思えるはずだと。
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
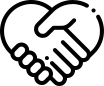 コラボPR
コラボPR
-
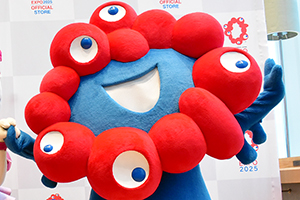
大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】
NEW 2025.4.18 17:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.4.10 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
2025.4.10 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
2025.4.10 11:00 -

大阪土産に悩んだら…これだ!駅近で買える人気5選[PR]
2025.4.9 07:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.4.2 19:30 -

春は桜も!ガイドブックにもない、淡路島秘境ツアー[PR]
2025.4.2 07:00 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】
2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版
2025.3.31 16:45 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]
2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]
2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]
2025.3.29 07:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]
2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ
2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]
2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.24 10:00 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]
2025.3.17 17:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.7 14:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年上半期の運勢は?
2024.12.29 20:00 -

京都や滋賀も舞台に…『光る君へ』年末年始に振りかえろう
2024.12.27 13:30 -

【大阪】梅田で忘年会&飲み会!大人数OKなおすすめ店12選
2024.12.10 11:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア

















 ピックアップ
ピックアップ







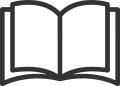 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

