2020年下半期に見逃していない? 観るべき洋画の評論家鼎談

モデル活動もおこなう主役のチュティモン・ジョンジャルーンスックジン。『ハッピー・オールド・イヤー』。(c) 2019 GDH 559 Co., Ltd.
斉藤「監督に『フィルムメーカーである』という自覚がないと無理」
斉藤「あと『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』もベスト3に入るね。監督が役者でもあるオリヴィア・ワイルド」
田辺「すばらしかったです。題材そのものはシンプルなんだけど」
斉藤「勉強漬けで遊んでいなかったのに、遊んでいた子の方が賢かったみたいな。しかも遊んでいた子らも良い大学に進学するもんだから、主人公は一夜で青春を取り戻そうとする話。主演は、ジョナ・ヒルの妹である、ビーニー・フェルドスタイン。明らかにジョナの出世作『スーパー・バッド 童貞ウォーズ』へのオマージュだからね」
田辺「キャスティングが見事でしたね」
斉藤「オリヴィア・ワイルドの夫であるジェイソン・サダイキスも出ていたりして、そのあたりのコメディ俳優のコミュニティを生かしている」
田辺「ジョナ・ヒルといえば、初監督作の『mid90s ミッドナインティーズ』が傑作でした」
斉藤「あれは永遠の青春映画。すべてが愛おしいんだよねえ」
田辺「スケボーを通して社会を知っていく。主人公の男の子がスケボー仲間に尋ねるじゃないですか、『黒人って何?』って」
春岡「あのシーンはゾクッとした。主人公の子は全く差別する気持ちはないんだけど。あれは良いよな」
斉藤「実際に今は、白人と黒人が一緒に住んでいるコミュニティの話が多くなっているよね。当たり前の話だけど今も差別はあるわけ。『ブラインドスポッティング』(2019年)みたいに、『一緒に生きてきたけれどもお前と俺の意識はやっぱり違う。僕とお前は同じなんだけど、受けてきた背景が違う」というものが今、増えてきてるのね」
田辺「それを13歳の男の子の目を通す。ジョナ・ヒル自身が見た1990年代中盤なんでしょうけど、多感さが映画にあらわれています」
斉藤「センスがあることは分かっていたけど、映画的に生きてきていたんだなって。だって妹が『ブックスマート』に出て、自分は『mid90s』だよ? そういう一族なんだな」
田辺「スケボーカルチャーもちゃんととらえていてね。スケボーで並走して8ミリカメラでローアングル撮影するところとか。僕も学生時代、ビデオでよくそういう映像作品を観ていました」
斉藤「スパイク・ジョーンズとかマイク・ミルズとかね。だから、ちゃんと自分の原点として、そういうカルチャーを再現したことに、ジョナ・ヒルの作家性を感じる」
春岡「被写体と映像撮影者が併走して撮っていく姿。それこそがあの時代のカルチャーだよな」
田辺「同じくスケボー少年たちが題材となったドキュメンタリー『行き止まりの世界に生まれて』も触れなければいけません。ラストベルトに暮らす若者たちの話で、未来に進もうとするけど行き止まりがある。それを地域性と絡めている」
斉藤「結果的には、前に進む方を向いていた。でも、あの映画って監督自身が過去と対決するところが1番の見どころやん?」
田辺「あの監督がお母さんに、義父の暴力について質問するインタビューシーン。あれってどうやって撮ったんだろう。技法的な意味ではなく、メンタリティって意味でね。だってお母さんのあの顔。息子に対して見せられる顔と言葉ではない。いろいろ超越している」
斉藤「あれは監督自身が『自分はフィルムメーカーである』という自覚がないと無理だよね」
春岡「『あれをやらなきゃ』ってこと。覚悟なんだよ」
斉藤「そう。それってジョナ・ヒルも同じだと思うのよ。まずはこれを撮らなくちゃ自分の青春時代は完結しないという気持ちが強くある」
春岡「ローティーンの頃の想いなんだけど、そういう青春を客観的に見ているところがあり、しかし覚悟を持って見つめないと結実しないってことだね」
田辺「その覚悟というのがDVの話なのがつらい。また、奇しくも今回の米国大統領選挙で焦点となるべき議題の数々ともリンクするところがある」

春岡「白人の低所得者層の世界というものが、俺たちの知ってるアメリカとはちょっと違うぞということだよね。しかしそれは1990年代からずっとあった」
斉藤「プアではないんだよね。『mid90s』の世界もそうだけど。だってもっと酷いクラスは、トレーラーハウスとかに住んでいるから。一応、サバービアに住んでるし、家もある」
春岡「そこはプアホワイトと呼ばれるところとの違いだよね。プアホワイトではない。日本人感覚で言うと、一応は中流みたいな感覚。でも決して裕福ではない」
斉藤「リーマンショックのときに餌食になった人がいっぱいいるの。家を手放さざるを得なくなったり。でもそれは『mid90s』以後の世界」
春岡「上手くいけばアッパーになっているかもしれないけど、でも現実は多分そうじゃない」
田辺「で、話は戻るけど監督は、自分の家庭と向き合う・・・というか、母親がうけていたDVを向き合って、涙を見なければならなくなる」
斉藤「でもあの場面がないと、この映画は締まらない。よくあれだけ撮ったよね、ホントに。自分の仲間のことも含めてさ。しかも、自分自身も悪い連鎖のなかにあるという部分も」
春岡「監督が撮っていた子もそうだけど、要するにアジア系でアメリカに今住んでいて、おふくろたちの世代には自分らの知らないアジア系としての苦労もいっぱいあって、それが分かっていく。そこのところも大事なんだよな」
田辺「クリント・イーストウッドの監督作なんかはそういうのをやってましたけどね」
斉藤「そうそう、全部引っかかってくるねん。『グラン・トリノ』もラストベルトの話だったし。社会派的アプローチでは『パブリック 図書館の奇跡』もおもしろかった。エミリオ・エステベスの監督・脚本作品。これがめっちゃ燃える映画。大寒波がやってきて、ホームレスたちが図書館に押し寄せて立てこもるのよ。もう、シドニー・ルメット監督の『狼たちの午後』(1975年)みたいなんだよ(笑)」
春岡「図書館を占拠するとか、左っぽい話じゃん」
斉藤「そうなんだけど、思想的に凝り固まってないのがいいのよね。スタインベックの『怒りの葡萄』を持ち出してきたりして、小ネタが効いてるの。あるレゲエの1曲とか。それで最後まで引っ張ったりして、脚本がとにかく上手い」
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
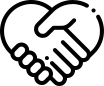 コラボPR
コラボPR
-
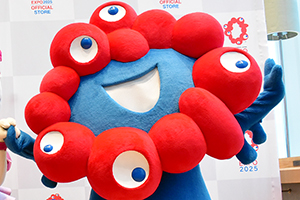
大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】
NEW 2025.4.18 17:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.4.10 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
2025.4.10 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
2025.4.10 11:00 -

大阪土産に悩んだら…これだ!駅近で買える人気5選[PR]
2025.4.9 07:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.4.2 19:30 -

春は桜も!ガイドブックにもない、淡路島秘境ツアー[PR]
2025.4.2 07:00 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】
2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版
2025.3.31 16:45 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]
2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]
2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]
2025.3.29 07:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]
2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ
2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]
2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.24 10:00 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]
2025.3.17 17:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.7 14:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年上半期の運勢は?
2024.12.29 20:00 -

京都や滋賀も舞台に…『光る君へ』年末年始に振りかえろう
2024.12.27 13:30 -

【大阪】梅田で忘年会&飲み会!大人数OKなおすすめ店12選
2024.12.10 11:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア
















 ピックアップ
ピックアップ







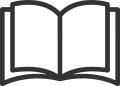 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

