SNSに囚われた女性と写真家「人から見られないと自分は存在しない」

淡々と趣味で写真を撮り、写真館ではリタッチがメインとなってしまっている械を演じる永井秀樹。(C)2020「写真の女」PYRAMID FILM INC.
今やレタッチが仕事となってしまった写真館の男、SNSを生業とする元バレエダンサーの女性の出会いを描いた映画『写真の女』。国内外の50以上の国際映画祭に出品され、グランプリを含む15冠を獲得するなど注目を集めている作品を撮影したのは串田壮史監督だ。
これまでCMディレクターとして活躍するほか短編映画を撮り、初めて長編作品のメガホンを撮ったのが同作。大阪では「第七藝術劇場」で2月27日から公開がスタートしたなか、串田監督に訊いた。
取材・文/ミルクマン斉藤
「日本ではインディーズ映画って、正面から劇場に向かっても上映してもらえない」
──僕は2020年の『大阪アジアン映画祭』で、ほとんど監督のプロフィールも知らない状態で拝見して興奮したのですが、なんでもイギリスで映画の勉強をされたんですって?
そうです。元々は大阪の出身で、地元の高校へ行って、大阪で2年間英語学科の大学に行ってたんですね。でも、英語学科って、多分4年勉強しても英語をしゃべれるようにならないんです(笑)。それに気付いてしまって、しゃべれるようになるにはこれは外国行くしかないな、と思って。
当時はすごくイギリスの映画がおもしろかったんですよ、『トレインスポッティング』とか『フル・モンティ』とか。そこで英語だけではなく、何かほかにも勉強した方がいいなと思って映画学科を探したんですね。
入学してみたらフィクションとかとは違って、例えば画面が明滅してるだけとか実験的な映像を作るところで、これはとんでもないところに来てしまったと(笑)。
──ああ、構造主義的な実験映画ですね。トニー・コンラッドとかポール・シャリッツとかマイクル・スノウとか、60~70年代くらいに流行った感じの。
そんな映像の学科にいたんで、郷に入れば郷に従えということで、僕もそんな実験的な映像を作っていましたね。
──僕も実は昔、8ミリフィルムでそちらの映像を作ってた人間なんですよ(笑)。なるほど、『写真の女』にもちょっとそんな匂いがありますよね。実際に編集のリズムと画だけで見せるというか。もちろん主人公の男に台詞がないということもありますけど。それとオール・アフレコの迫力。なにげない音や聞こえるはずのない音を拡大してみせるとか。そういうところに普通の劇映画としては収まりきらないところが多くある。
言葉が分からない人でもなんとなく怒っているのか楽しんでいるのか分かりますよね。例えば食事中だったらフォークを置くときの音の大きさとか、そういうところから感情って伝わるものだと思うんです。
だからこの映像ではそれを適切にコントロールしたかったので、全部アフレコにして、全部の音をあとで調整できるようにしました。
──なるほど。それはトーキー映画の本来の美点でもあるんですけどね。
そうですね。でも最近の映画とは逆の方向だと思うんですよ。例えばスマホで見られることを意識してか、しゃべってる人のクローズアップが多いんです。それに登場人物があまり多くなくて、すごく分かりやすく作ってると思うんです。
電車のなかで見てる人もいるから、音なんて出さずに見たり、音の演出というのが多くなくて。ですからこの映画の手法というのは、今だとほかの映画とちょっと違う手法だと思われるかもしれないですね。

──反対に、今映画でしか味わえないものを見せてやる、って意味も大きいと思います。むしろ、そっちの方が映画言語的には正解だと思うんですけどね。
映画言語というのは世界共通だと思うんですよね。ヴーンって言う低音が流れれば緊張感とか、チュンチュンって鳥が鳴けば翌日とか。その文法というのは世界共通なんで、すごく重要な感じだなと。
日本ではインディーズ映画って、正面から劇場に向かっても上映してもらえないんですね。一度、海外の映画祭で上映して、その間に評判を得ることによって映画館の人が上映してみようかなと思うものなので、まず外国の人が見ても分かるように作ろうと考えましたね。
──その意味では、少なくとも主人公のひとりである写真家は最後まで言葉を発さないので万人に捉えやすいですよね。僕が2020年の『大阪アジアン映画祭』で拝見したときには、すでに海外の映画祭を回られていたんですか?
あれがワールド・プレミアだったんです。完全に完成したのは大阪アジアンの締め切りの前の日だったんですよ(笑)。そのあと外国の映画祭はコロナのせいで全部オンラインになって。
でもこの作品についてはポジティブに働いたところが大きいです。結構すごいお金をつぎ込んで大きく戻さないといけない作品は映画祭に出すのを延期したんだけど、僕の作品はイケイケだったんで(笑)。例年よりも映画祭に入選しやすい年だったんですよ。
──いやいや、それは謙遜というもので、立派な受賞歴ですね。まず写真というか映像というか、そんなものの立ち位置が数年で劇的に変わってしまった。この映画の主人公はおそらく実家の仕事を継いだ二代目か三代目の写真館の主人ですけど、昔のように家族の肖像であるとか、冠婚葬祭であるとか、何かの記念、記憶のためのツールから、自分を他人にアピールするツールへと急速に変わってしまった。
そうですね。おっしゃるとおり写真というものがすごく変わったというのは、この10年20年の間にすごく感じているんですね。街の写真屋は次々と潰れたけど、写真が撮られる数は劇的に増えているんですよ。
聞いたところでは2020年の1年間で撮られた写真の数は、これまで人間の歴史のなかで撮られてきた写真の2倍なんだと。それぐらいみんながパシャパシャ撮るようになってるんですよ。
でも僕は、SNSで自分を見せるというのは日本人にすごくフィットしてると思ったんです。しかも加工修正するしてから見せるというのを礼儀のように感じてる人がいるんですね。みんなと同じような写真をあげなければいけないという。
──非現実的なまでに目を大きくしたりする加工ソフトなんかを使う人の気持ちが、正直僕はよく分からないんですけどね(笑)。
プリクラの時から続いてるんですよ。プリクラってアメリカとかで流行ってるの見たことなくって。やっぱりみんな同じ顔になるっていうのはすごく日本的というか。
同調性というんでしょうか、「人のことを考えましょう」とか、「友達をいっぱい作りましょう」とか、そんな学校教育の延長線上で受け入れられたと思うんですね。インスタグラムであそこまで加工修正するのも東アジア土着の、なんか村意識というのか、みんなと同じでいなければいけないとか。
『写真の女』
脚本・監督:串田壮史
出演:永井秀樹、大滝樹、猪俣俊明、鯉沼トキほか
配給:プラミッドフィルム
(C)2020「写真の女」PYRAMID FILM INC.
関西の映画館:第七藝術劇場(2月27日〜)
 関連記事
関連記事
 あなたにオススメ
あなたにオススメ
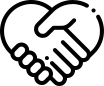 コラボPR
コラボPR
-

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版
NEW 12時間前 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版
NEW 15時間前 -
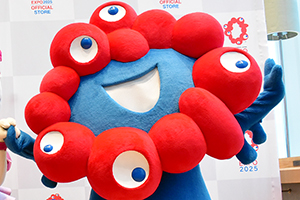
大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】
NEW 22時間前 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]
NEW 2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]
NEW 2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]
NEW 2025.3.29 07:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.28 16:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫
2025.3.28 14:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]
2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ
2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]
2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.24 10:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版
2025.3.19 10:30 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]
2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]
2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]
2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版
2025.3.7 14:00 -

今が旬!大阪難波であまおう苺のアフタヌーンティー[PR]
2025.3.6 17:00 -

万博まで待てない!神戸でサウジアラビアパビリオンを体験[PR]
2025.3.6 12:00 -

万博内2番目に大きなパビリオン!サウジが難波に[PR]
2025.3.5 17:00 -

高速料金が乗り放題でお得!ぐるっとドライブパス[PR]
2025.3.1 10:00



 トップ
トップ おすすめ情報投稿
おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは
Lmaga.jpとは ニュース
ニュース まとめ
まとめ コラム
コラム ボイス
ボイス 占い
占い プレゼント
プレゼント エリア
エリア













 ピックアップ
ピックアップ







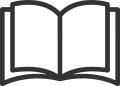 エルマガジン社の本
エルマガジン社の本

